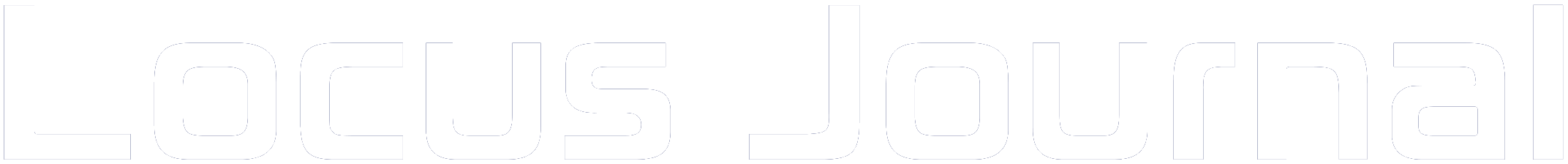お客様から注文を受けたら、商品を発送するために出荷作業を行います。お客様が注文した商品に破損や傷がないかを検品して指定日に配送しなければいけません。慌ただしい中で出荷ミスを防ぐには、どうすればよいのでしょうか?
今回は出荷作業について詳しく解説します。この記事を読めば、出荷ミスを減らすための対策まで理解できるようになるため、ぜひ読んでみてください。
出荷とは

商品を倉庫に受け入れる入荷に対して、注文情報を元に商品を発送するために行う作業が出荷です。梱包や送り状をつけるなどの作業も含まれます。倉庫の商品を出荷するまでの流れは以下のようになります。
出荷登録
受注データをWMSに登録、出荷指示データを作成します。
在庫引き当て処理
WMSから在庫情報を確認して、出荷指示データに基づいた在庫の引き当てを行います。
ピッキング
ピッキングとは「保管場所から必要な物品を取り出す作業」を指します。(JIZ 0111:2006)特に出荷指示に基づいて物品を保管場所から取り出す作業のことをオーダーピッキングと呼びます。
ピッキングについては、以下の記事で詳しく説明しています。
関連記事:『ピッキングとは?ピッキング種類から業務効率化の方法まで徹底解説』
検品
検品では、ピッキングした品物と出荷指示データが一致しているかを確認、さらに品物に破損などがないかをチェックします。
検品については、以下の記事で詳しく説明しています。
関連記事:『検品とは?検品作業をミスなくスピーディに改善する方法を徹底解説!』
梱包
梱包では、商品を発送する際に箱、梱包材などで商品を保護する作業です。
発送
発送とは、梱包した荷物を運送業者へ渡し、送り出す作業のことです。似た言葉である配送は、「貨物を物流拠点から荷受人へ送り届けること。」です。(JISZ 0111:2006)
出荷と出庫・発送・配送・集荷の違いについて
出荷と似た用語として「出庫」「発送」「配送」「集荷」があります。これらの違いは以下の通りになります。
出庫との違い
出荷と出庫の違いは「送り先」です。
出荷とは顧客に受注商品を発送して売上を計上することをいいます。その一方で、出庫は支社の倉庫や配送センターに商品を発送することをいい、売上は計上されません。このように、出荷と出庫は送り先が異なります。
発送との違い
出荷と発送の違いは「作業単位」です。出荷とは「出荷登録」「在庫引き当て処理」「ピッキング」「検品」「梱包」「発送」の一連の作業をいい、発送とは商品の発送作業のみをいいます。つまり、出荷作業に発送作業が含まれています。
配送との違い
出荷と配送の違いは「作業内容」です。
出荷とは、出荷登録から発送作業の倉庫内で行う作業をいいます。その一方で、配送とは商品が積まれたトラックを運転して、配達先に商品を届ける作業をいいます。つまり、出荷と配送は全く異なる作業です。
集荷との違い
出荷と集荷の違いは「作業単位」です。
出荷は出荷登録して、商品を梱包して発送する一連の作業をいい、集荷とは発送したい商品を運送会社に取りにきてもらう作業をいいます。つまり、出荷作業に集荷作業が含まれています。
出荷の重要性について
出荷は顧客に品物を送り出すプロセスのため、出荷でミスがあると顧客からの信頼が低下する恐れがあります。さらに効率化の点からも出荷を正確に行うことは重要です。
品違い、数量違い、配送先間違いなどにより誤った商品を出荷してしまうことを誤出荷と言います。顧客からのクレームにより発覚・把握した件数を計測します。
物流業界では、品質管理の指標として誤出荷率(PPM:Parts Per Million、100万件の出荷に対して何件誤出荷が発生したか)を用いることがあります。
誤出荷発生件数÷作業総件数×1,000,000で求めることができ、10PPMが理想的と言われています。平均値は276PPM、大手飲料メーカーのキリンでは、5.6PPMという高い数値を実現しています。
よく起こる出荷ミスと原因
誤出荷の原因となる5つの原因を紹介します。いずれもヒューマンエラーで起こるミスであり、システムにより改善できる可能性が高いです。
商品のタイプ間違い
商品のタイプ間違いは、同一品番でサイズや色が異なる品物を出荷するミスです。品番だけ見てピッキングし、それ以外のサイズや色コードを見落とすなどの原因が考えられます。
商品点数の間違い
商品点数の間違いとは、出荷指示と実際のピッキング個数が一致しないミスです。ピッキング時の指示書読み間違いなどの原因が考えられます。
送り先の間違い
送り先の間違いとは、品物を注文した顧客とは異なる相手に送ってしまうミスです。原因は、送り状作成時にデータが違った場合と、伝票の貼り間違いなどの場合があります。
品番の間違い
品番の間違いとは、出荷指示と異なる品番の商品をピッキングしてしまうミスです。目視で品番をチェックして品番を間違えるなどの原因が考えられます。
付属品の同梱忘れ
付属品の同梱忘れとは、出荷時に、必要な同梱物を入れ忘れるミスです。品物と同梱物が適切に管理されていない場合に起こりやすくなります。
出荷ミスを減らすための対策
出荷ミスを減らすための方法は、ミスが起こりにくい環境づくりとミスが起きてもカバーするためのチェック体制、そしてそもそもミスが起きないようシステム化することです。
チェック体制を整える
1つ目は、ミスが発生しても早期に発見できるようチェック体制を整える方法です。1人だけでなく2人以上でチェックするダブルチェックを行うことで、ミスが表に出ることを減らします。
出荷スペースを確保する
2つ目は、作業環境を整えてミスが起きにくくする方法です。作業間違いを減らすために、充分な作業スペースを確保するといった対策が有効です。
WMS(倉庫管理システム)を導入する
WMS(Warehouse Management System)とは、商品の入出庫や保管の正確性と効率アップを支援する目的のシステムです。WMSにより商品をデータで管理することができ、ミスの軽減が期待できます。
WMSについて詳しく知りたい方は、下記の記事を読んでみてください。
関連記事:『WMS(倉庫管理システム)とは?導入のメリット・デメリットや選定のポイントを解説』
システム化して人の関与を減らす
システム化によりヒューマンエラーを防止するのも有効です。バーコード/RFIDによる管理システムを導入することで、ミスの低減、省人化を実現します。ピッキングロボット導入によりピッキングミスを削減できます。
まとめ
出荷作業とは、注文情報を参考にしながら商品を発送していく作業です。正確に作業を行わなければ、商品サイズの間違いや商品点数の間違いなど出荷ミスが起きてしまい、注文者に迷惑がかかります。そのため、出荷ミスを減らすための対策を打っておきましょう。
この記事では、出荷ミスを減らすための対策をご紹介しました。出荷作業を効率的に正確に行いたいという方は、これを機会に作業を見直してみてください。