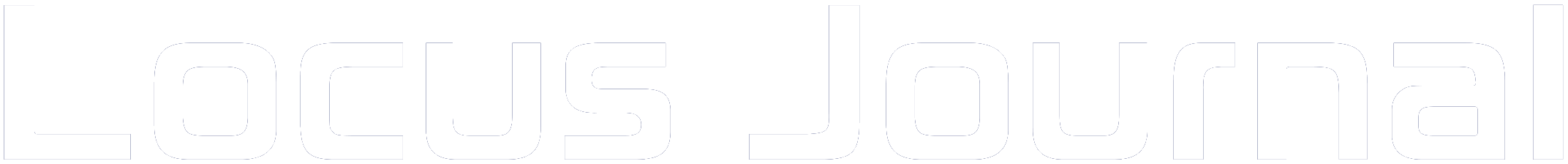近年、仮想空間を活用した「メタバース」と「デジタルツイン」が高い注目を集めています。両者は似て非なるものですが、それぞれの特徴や違いをしっかりと理解しているという方は少ないかもしれません。
そこで今回は、メタバースとデジタルツインの基本概念に触れながら、2つの違いやメリット、デメリット等について詳しく解説します。あわせてデジタルツインの活用事例も紹介しますので、参考にしてみてください。
メタバースとデジタルツインの違い
メタバースとデジタルツインは、どちらも仮想空間を使った先進技術ですが、目的や対象、技術用途等に大きな違いがあります。ここでは、メタバースとデジタルツインのそれぞれの特徴を確認するとともに、両者の違いについても詳しく解説していきます。
メタバースとは
メタバースは、超越や高次元を意味する「メタ(Meta)」と宇宙や世界を意味する「ユニバース(Universe)」を組み合わせた造語で、インターネット上に構築された3次元の仮想空間を指します。
ユーザーは自身の分身であるアバターを通して、仮想空間の中で他のユーザーと自由にコミュニケーションをとったり、ゲームや会議、イベントに参加したり、ショッピングをしたりとさまざまな体験ができます。
VR(仮想現実)やAR(拡張現実)と連携することで、これまでにない臨場感あるコミュニケーションを実現できる点が大きな特徴で、近年では、ビジネスや教育分野などでも活用が広がっています。
関連記事:https://blog.rflocus.com/what-is-metaverse/
デジタルツインとは
デジタルツインは、現実のモノや仕組みを仮想空間に再現する技術を指します。センサーやIoTを使って集めたデータをもとに、機械の動きや工場の状況などをリアルタイムで再現・分析します。
デジタルツインを活用することで、トラブルの予測や作業の効率化、安全性の向上などが期待できます。そのため、製造業をはじめ、インフラ、建設、エネルギーなど、多様な分野で活用が進んでいます。
関連記事:いまさら聞けない「デジタルツイン」とは|メリットや課題、製造業における活用事例を解説
メタバースとデジタルツインの違い
メタバースとデジタルツインは、どちらも仮想空間を活用する点で共通しますが、目的や活用分野、目指す価値などに以下のような違いがあります。
|
メタバース |
デジタルツイン |
|
|
主な目的 |
体験・交流・ コミュニケーションの提供 |
現実のモノ・仕組みの 再現と最適化 |
|
活用分野 |
エンタメ、SNS、 教育、ビジネス など |
製造業、インフラ、 建設業、エネルギー など |
|
仮想空間の 役割 |
現実とは別の「もう一つの 世界」を構築し、ユーザーの 自由な活動を可能にする |
現実の状態をリアルタイムで 再現し、シミュレーションや 予測に活用 |
|
データとの関係 |
必ずしも現実のデータと連携しない(空想的な世界も含まれる) |
IoTやセンサーで集めた 現実のデータと常に連携 |
|
目指す ゴール |
没入体験や新たな価値創造 ユーザー同士の交流 |
現場業務の効率化、安全性向上、 コスト削減、品質向上 など |
つまり、メタバースが人の体験を豊かにするためのツールであるのに対し、デジタルツインは、現場やモノの課題を解決するための実務的なツールであるといえるでしょう。
デジタルツインのメリット
デジタルツインの活用により期待できるメリットは以下の通りです。
- コスト削減・効率向上
- リスク低減・安全性向上
- 意思決定の迅速化・高度化
- 製品・サービスの品質向上
- サステナビリティ・環境貢献
それぞれのポイントについて詳しく確認していきましょう。
コスト削減・効率向上
デジタルツインを活用すれば、実際の設備やプロセスの挙動を仮想空間で正確に再現できます。設備や機会を稼働させなくても、仮想空間内で最適化が行えるため、設備投資や実地検証にかかるコストを大幅に削減できます。
また、シミュレーション結果をもとに効率的なレイアウトや稼働スケジュールを事前に検証できるため、ダウンタイムの最小化や無駄の排除にもつながります。
リスク低減・安全性向上
デジタルツインは、設備やシステムの状態をリアルタイムで監視し、異常の兆候を早期に検知できます。これにより、事故やトラブルの予測が可能となり、計画的な保守運用やリスク回避が可能になります。
また、危険な作業や高温・高圧等、過酷な条件下での実験をデジタル空間で代替できるため、現場の安全性の大幅な向上も期待できます。
意思決定の迅速化・高度化
デジタルツインを活用することで、リアルタイムデータをもとにした迅速かつ精度の高い意思決定が可能になります。従来は経験や勘に頼っていた領域でも、データドリブンな意思決定が進むため、経営や現場での問題解決がスピーディーかつ的確に実現できるようになります。
さらに、AIと連携すれば、特定の判断を自動化し、人間の負担を軽減しながら意思決定の質を高めることも可能となります。
製品・サービスの品質向上
デジタルツインを活用すれば、製品の設計段階から高精度なシミュレーションや検証が可能になります。試作前に不具合や性能の問題を特定できるため、製品開発サイクルを短縮しながら、耐久性、性能、使いやすさなどの品質を高められます。
また、実際の使用データや顧客の利用状況をリアルタイムで分析することで、サービス改善や個別ニーズへの対応も迅速に行えます。
サステナビリティ・環境貢献
デジタルツインは、サステナビリティの推進や環境負荷の低減にも大きく貢献します。たとえば、電力使用量や排出ガス、廃棄物量などのデータを可視化し、最適なエネルギー使用計画を策定することで、環境負荷の低減を実現できます。
また、再生可能エネルギーの導入効果を定量的に評価することも可能なため、環境経営の強化にもつながります。
デジタルツインを実現させるための技術
デジタルツインを実現するには、現実世界の情報を収集・再現・分析・可視化する以下のような技術との連携が不可欠です。
- AI(人工知能)
- IoT(Internet of Things/モノのインターネット)
- XR(クロスリアリティ)
- 5G(第5世代移動通信システム)
- CAE(Computer Aided Engineering)
それぞれの技術の概要とデジタルツインにおける役割について解説します。
AI(人工知能)
AIは、大量のデータからパターンや因果関係を学習し、予測・最適化・自律的な意思決定を行う技術です。
デジタルツインにおいては、収集されたセンサーデータを解析し、システムの状態をリアルタイムで判断する、将来の故障や異常を予測するなどの役割を担っています。また、複数のシナリオをシミュレーションして最適な運用方法を導き出すことも得意としており、運用の効率化やリスクの回避にも寄与しています。
こうしたAIの機能により、デジタルツインは単なる可視化ツールではなく、状況を先読みし、よりよい選択を支援する判断力のある仕組みへと進化しています。
関連記事:人工知能・AIとは?基本知識から、IoT x AIの製造業での活用事例や注目サービスまで徹底解説
IoT(モノのインターネット)
IoTは、Internet of Thingsの略称で、センサーやデバイスをネットワークにつなぎ、物理世界の情報をリアルタイムでデジタルに収集・送信する技術を指します。
デジタルツインにおいては、工場設備、建物、車両といった現実の対象物からデータを取得し、仮想空間上にその情報を反映させる橋渡しの役割を担っています。
IoTがなければ、デジタルツインは現実世界の変化をとらえることができず、静的なモデルにとどまってしまいます。つまり、デジタルツインを生きたモデルとして機能させるために、IoTは欠かせない技術といえます。
関連記事:IoTとは?IoTの最新動向と活用事例をわかりやすく解説
XR(クロスリアリティ)
XRは、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)といった技術の総称で、現実世界と仮想世界を融合させる技術を指します。デジタルツインにおいては、可視化のインターフェースとしての役割を担っており、複雑なシステムの内部構造や稼働状況の直感的な把握を可能にしています。
たとえば工場の設備管理や都市インフラの点検などでは、作業員が現場でARゴーグルを着用し、仮想モデルと現物を重ね合わせて確認を行うといった使い方がされています。また、遠隔地にいる専門家が同じ仮想空間を共有し、現場の作業者に指示を出すなどの応用も進んでいます。
5G(第5世代移動通信システム)
5Gは、超高速・低遅延・多数同時接続を実現する次世代通信技術です。デジタルツインでは、IoTデバイスから大量のデータをリアルタイムに送受信する必要がありますが、5Gはその通信基盤として欠かせない役割を担っています。
たとえば、わずかな遅延がシステムの安全性に関わる自動運転車やスマート工場の分野においては、5Gの高速・低遅延通信が極めて重要とされています。また、工場内に配置した多数のIoTデバイスから同時かつ大量にデータを集めて制御する際にも、5Gがスムーズな連携を可能にしています。
CAE(Computer Aided Engineering)
CAEは、構造解析、熱解析、流体解析などを含む、設計や製造におけるシミュレーション・解析技術の総称を指します。デジタルツインにおいては、現実世界の挙動を仮想空間に忠実に再現するための実験装置のような役割を担っています。
CAEを活用すれば、航空機の部品や建築構造物の強度や耐久性をリアルタイムに検証する、システム全体のパフォーマンスを予測するといったことが可能になります。つまり、CAEはデジタルツインの物理的な正確さや信頼性向上に大きく寄与する技術のひとつといえます。
デジタルツインの活用事例
デジタルツインの活用は、さまざまな業界、業種で進んでいます。ここからは、デジタルツインの活用により、業務効率化や安全性向上を実現した事例を5つ紹介します。
富士通
富士通は、2023年に行われた「第7回スマート工場EXPO」で、「Actlyzer(アクトライザー)」と呼ばれるAI映像解析技術使った新たなデジタルツイン化ソリューションを発表しました。Actlyzerは、作業者の行動や装置との関係性を3次元で認識し、生産ラインのデジタルツインに自動反映する仕組みです。
既設のカメラの映像から、装置操作や作業内容を高精度に再現できるため、予兆保全や作業改善に活用されています。従来必要だったカメラキャリブレーションも不要なため、導入ハードルが低いのも特徴で、スマート工場の実現に大きく貢献しています。
参考記事:「行動分析技術Actlyzer」で製造分野のデジタルツインを実現する新技術を開発し、「第7回スマート工場EXPO」に出展
旭化成
旭化成はデジタルツインを活用し、自社の水素製造プラントの設備運転状態をリアルタイムで監視・シミュレーションしています。プラント内の流体や温度、化学反応の挙動を仮想空間に再現することで、製品品質の安定化や異常兆候の早期発見を実現しています。
この取り組みにより、ベテラン技術者が現場に常駐せずとも、遠隔地からでも設備状況をリアルタイムに把握できるようになりました。異常発生時には的確な指示をすぐに出せることから、安全性の向上や、ダウンタイムの削減、ベテラン技術者の現場負担軽減にも寄与しています。
参考記事:旭化成の水素製造プラントで「デジタルツイン」、ベテランが異常対応をどこでも支援
日立
日立製作所は、2018年10月、生産現場のデジタルツイン構築を支える統合プラットフォーム「IoTコンパス」の発売を正式発表しました。IoTコンパスは、生産現場のOT(制御・運用技術)とITデータを統合し、生産工程全体を可視化・最適化できるソリューションです。
最大の特長は、「4M(人・機械・材料・方法)」の情報を組み合わせて、生産の流れをリアルタイムで再現できる点で、品質のばらつきやムダの早期に発見に役立っています。
IoTコンパスは、スマート工場の実現に向けた日立の中核ソリューションとして、多くの製造業での活用が期待されています。
参考記事:生産現場デジタルツイン化ソリューション「IoTコンパス」
鹿島建設
鹿島建設は、大阪府の「オービック御堂筋ビル」の建設プロジェクトで、日本で初めて建物の全てのフェーズ(企画・設計・施工・運用)においてBIM(Building Information Modeling)を活用したデジタルツインを実現しました。
具体的には、設計段階では風の流れや空気の動きなどをシミュレーションし、快適な空間設計を行うために、施工中はBIMモデルと現場の状況をMR(複合現実)で照らし合わせ、施工ミスを減らしながら作業の効率を高めるために、デジタルツインが活用されました。さらに、完成後も建物の点検情報や設備データをBIMに集約し、管理や運用に活かしています。
この取り組みにより、同社は設計と施工の効率化、現場の安全性向上、維持管理コストの削減、建物資産価値の強化など、多くの成果を実現しました。
参考記事:日本初!建物の全てのフェーズでBIMによる「デジタルツイン」を実現
ダイキン
ダイキンは大阪・堺製作所臨海工場で、2020年よりデジタルツイン対応の生産管理システムを本格稼働させました。工場内の各作業工程にはセンサーとカメラを設置し、部品の流れや作業者の動き、設備稼働状況をリアルタイムでバーチャル工場に再現しています。
このシステムでは、作業の遅延や設備異常を事前に察知し、アラートを出すことで迅速な対応を促す仕組みがとられています。導入後はラインの停止による時間とコストロスを約3~4割削減し、「止まらない工場」の実現に大きく貢献しました。
さらに、センサーのデータ収集とシステム開発を自社育成のDX人材が主導しているのも特徴で、製造業におけるデジタル変革の優れたモデルとして注目を集めています。
参考記事:ダイキンが工場の「デジタルツイン」、製造ラインの停滞予測しロス3割強減へ
まとめ
メタバースとデジタルツインは、どちらも仮想空間を活用するという点では共通していますが、その役割や使われ方は大きく異なります。
特にデジタルツインは、ものづくりや社会インフラなど、現場の課題解決に直結する技術として注目が高まっています。近年では、業務効率化や品質向上、リスク低減などの成果を求めて、製造業や建設業をはじめ、エネルギー、医療、都市開発など、幅広い分野でデジタルツインの導入を進める企業が増えています。
メタバースやデジタルツインといった仮想空間を活かした技術が現実世界にもたらす価値は、今後さらに広がっていくことが予想されます。導入を検討する場合、まずはその違いや特性を正しく理解し、自社にとってどのような可能性があるかを見極めること重要です。