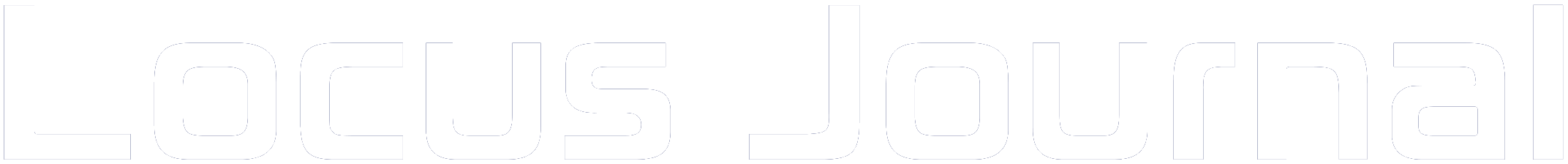通信インフラ技術の進化や、オフラインコミュニケーションの需要増加などの背景から、注目を集めている「メタバース」。近年では、ゲームやビジネス、教育などさまざまな分野で活用が広がり、私たちの暮らしや働き方にも大きな影響を与え始めています。
しかし、名前は聞いたことがあるが、具体的にどのようなものかわからない、VRとの違いがわからないという方も多いかもしれません。そこで、今回は、メタバースの基礎知識からVRとの違い、主要な活用分野やおすすめのメタバースプラットフォームまで、わかりやすく解説します。
メタバースとは
メタバース(Metaverse)とは、「Meta(超越した)」と「Universe(宇宙)」を組み合わせた造語で、インターネット上に存在する3次元の仮想空間を指します。ユーザーはアバターと呼ばれる仮想の分身を使ってこの空間を移動し、他のユーザーとの交流や買い物、ゲーム、イベント参加など、多様な活動を行います。
近年では、教育や医療、ビジネスの場でもメタバースの活用が広がっており、「もう一つの社会」や「第二の経済圏」とも呼ばれています。
さらに、ブロックチェーンやNFT、AIなどの先端技術と結びつくことで、リアルと仮想の境界が曖昧になるような新しい体験も可能となっています。
VRの違い
メタバースとともに近年、耳にする機会が増えているのが「VR(Virtual Reality・仮想現実)」です。両者は混同されがちですが、実際には概念や目的、必要な機器等に違いがあります。
|
メタバース |
VR |
|
|
概念 |
インターネット上の仮想空間全体 |
仮想現実を体験するための 技術・装置 |
|
目的 |
人々の交流、活動、経済圏の構築 |
没入型体験、シミュレーション |
|
必要機器 |
マルチデバイス対応 (PC、スマホ、VR機器など) |
主にVRヘッドセットや コントローラー |
VRは視覚や聴覚を中心に仮想空間を体験する技術を指し、利用にはVRヘッドセットなどの機器が必要です。
一方、メタバースはその技術を活用した「仮想空間の中の世界」や「体験そのもの」を指します。つまり、VRはあくまで体験手段の一つで、メタバースはそれを含むより広範な概念といえます。
メタバースが注目される理由
メタバースが注目されている理由として挙げられるのは、大きく以下の5点です。
- 市場規模の大きさ
- 通信技術・VR技術の発展
- 大手企業の参入
- NFTとの親和性の高さ
- オンラインコミュニケーションの進化
それぞれについて詳しく確認していきましょう。
市場規模の大きさ
メタバース市場は近年、急速に拡大しています。デジタル広告やゲームのみならず、教育、医療、ファッション、製造業等、あらゆる分野にメタバースの可能性が広がっており、2030年には市場規模が数百兆円に達すると予測されています。
また、NFTや仮想通貨の普及、個人から企業・行政までメタバースを活用するプレイヤーが急増している点も、注目を集めている要因の一つとして挙げられます。
通信技術・VR技術の発展
メタバースの発展は、通信インフラやVR・AR技術の進化と密接に関係しています。たとえば、5Gが普及したことで、高速かつ低遅延の通信が可能となり、リアルタイムの映像・音声コミュニケーションや、大人数が同時参加する大規模イベントが実現しました。
また、VRゴーグルやARデバイスの高性能化・低価格化により、一般ユーザーでも気軽にメタバース体験ができるようになった点も、メタバースの成長を大きく後押しする要因となっています。
大手企業の参入
世界的な大手企業が相次いでメタバース分野に参入していることも、注目度が高まる理由の一つとして挙げられます。
海外企業では、2021年に米・Facebook社が社名を「Meta」に変更し、メタバースを中核事業に据えることを発表したのは記憶に新しいでしょう。Facebook社の他にも、Microsoft、Google、Apple、Tencentなど、世界を代表する巨大IT企業も、独自のプラットフォームや関連技術の開発に積極的に取り組んでいます。
また、国内ではサイバーエージェントやグリーなどのIT企業だけでなく、NTTやソニー、トヨタなどの企業もメタバース業界への参入を表明しています。こうした大手企業が参入することで市場の信頼性が増し、投資家や参加ユーザーの増加も加速しています。
NFTとの親和性の高さ
NFT(非代替性トークン)とは、「Non-Fungible Token」の略称で、他のものと代用できない、唯一性を持つデジタルデータの所有や真贋を証明する仕組み(デジタル証明書)を指します。メタバースはNFTと親和性が高く、この点もメタバースが注目される背景の一つとされています。
NFTはデジタルデータの唯一性や所有権を証明できるため、メタバース内でのアバター、アイテム、土地などの資産管理に役立ちます。また、NFTを使えばユーザー間での売買やレンタル、クリエイターへのロイヤリティ還元も可能になります。
将来的に、NFTが複数のメタバース間で利用できるようになれば、仮想空間内での経済活動が活発化し、メタバースがクリエイターの新しい活躍の場となる可能性も高くなります。
オンラインコミュニケーションの進化
コロナ禍で対面での交流が制限されたことを契機に、非対面・非接触で人とつながる新たなコミュニケーション手段への需要が高まりました。アバターを通じて仮想空間で交流できるメタバースは、従来のビデオ通話やチャットでは得られない高い没入感や臨場感をユーザーに提供します。
その結果、メタバースは娯楽だけでなく、教育やビジネスなど幅広い分野に活用されるようになりました。今後は技術の進化とともに、よりリアルで直感的な体験が可能となり、私たちのコミュニケーションの在り方そのものを大きく変えていくことも期待されています。
メタバースの活用分野
メタバースの活用分野は以下のように多岐に渡ります。
- ゲーム
- ビジネス
- ショッピング
- イベント・ライブ
- LAND(土地)
それぞれの分野でメタバースがどのように活用されているか詳しく確認していきましょう。
ゲーム
メタバースはゲーム分野で最も早く普及し、仮想空間の中で他のプレイヤーとリアルタイムに交流・対戦できる環境を提供しています。
特に、「Fortnite」「Roblox」など、メタバースの先駆け的存在とされる人気タイトルでは、ゲームを楽しむだけでなく、ユーザーがコンテンツを制作したり、自身のアバターを通じて社会的な体験したりする場にもなっています。
近年では、ユーザー参加型のゲーム開発や教育的要素も取り入れられるなど、メタバースが単なる遊びの枠を超え、新たな文化・経済圏を生み出しています。
ビジネス
メタバースはビジネスの新たなプラットフォームとして注目されており、会議や研修、バーチャルオフィスの構築などに活用されています。特にリモートワークが一般化した昨今では、従業員同士のコミュニケーションの質の向上や、エンゲージメントを維持する手段としてメタバースを活用する企業も増えています。
また、メタバースは、企業ブランディングやマーケティングでも活用が進んでいます。たとえば、バーチャル空間上で製品発表イベントを行ったり、顧客がブランドの世界観を体験できる仮想店舗を展開したりなど、従来とは異なる顧客体験を創出する動きが加速しています。
ショッピング
メタバースはショッピングの分野でも活用されており、顧客に以下のような新たな没入型の購買体験を提供しています。
- バーチャル店舗の開設
企業がメタバース内に仮想店舗を構築。ユーザーはアバターを使って実際に店内を歩き回りながら、商品を見たり選んだりできる
- アバター向けデジタル商品の販売
企業がアバター専用のデジタルファッションやスキン(見た目)を販売
- 試着・シミュレーション体験
AR(拡張現実)や3Dモデリングと連携することで、洋服やメガネ、靴などバーチャル試着や、化粧品等のシミュレーションを体験
- イベント型ショッピング体験
メタバース内でポップアップショップやコラボ商品発売などの限定イベントを実施
また、メタバース内で商品を体験・試着した後に、ECサイトへシームレスに移動して実際の商品を購入できる仕組みも整いつつあり、現実と仮想の垣根を超えた新しい消費スタイルが生まれています。
イベント・ライブ
アーティストのバーチャルライブやファッションショー、企業の製品発表会など、イベントやライブをメタバースで行うケースも増えています。
メタバースを活用することで、世界中のユーザーがイベントに参加できるのはもちろん、参加者が応援メッセージを送ったり、アバターを通してジャンプしたりなど、インタラクティブな体験が可能になります。
また、制限のないメタバース空間を利用すれば、現実世界では実現が難しい演出やステージ展開が可能となり、より没入感の高いイベントやライブが実現できる点も大きな特徴といえます。
LAND(土地)
LANDは、仮想空間上に存在する土地のことで、ユーザーや企業が所有・活用できるデジタル資産を指します。代表的なプラットフォームである「Decentraland」や「The Sandbox」では、NFT技術を用いてLANDが売買され、所有者はその土地に店舗、ギャラリー、住宅などを自由に構築できます。
広告拠点やバーチャルショップとしてLANDを活用する企業や、自身の作品の展示場として利用する個人プレイヤーも増えており、新しい経済活動の基盤としても高い注目を集めています。
また、LANDは現実の不動産のように需給に応じて価格変動が起こります。そのため、投資の対象として、資産運用に活用されるケースも増えています。特に人気の高いエリア、有名ブランドや著名人の近隣に位置するLANDは価値が上昇しやすく、将来的な値上がりを見込んだ投資家が参入する動きも活発になっています。
メタバースのメリット
メタバースを活用する主なメリットは以下の通りです。
- 新たなユーザー体験の提供
- 物理的制約がない
- ビジネスチャンスの拡大
それぞれのポイントについて詳しく確認していきましょう。
新たなユーザー体験の提供
メタバースは、従来のインターネットやリアルな空間では味わえなかった没入型の体験を提供します。ユーザーは、三次元空間内で他者とリアルタイムに交流したり、アバターを通じて自己表現をしたりすることで、より直感的で感覚的なコミュニケーションを楽しめます。
たとえば、仮想のライブ会場でアーティストと同じ空間を共有する、世界中の人と同じ空間で会議や授業に参加する等の経験は、メタバースならではといえます。
今後、メタバースの活用がさらに進めば、私たちの生活様式や働き方、教育、娯楽の在り方に大きな変化がもたらされる可能性が高くなります。
物理的制約がない
メタバースは地理的・時間的な制限を超えて活動できる空間をユーザーに提供します。たとえば、メタバースを活用することで、遠隔地に住む人同士がまるで隣にいるかのように会話したり、物理的に存在しない仮想オフィスで共同作業したりできるようになります。
また、現実の空間ではアクセスが難しい場所への移動や体験も、メタバースを活用すれば誰でも簡単に実現できる点も、大きなメリットです。身体的な制約がある人でも、アバターを通じて自分の望む姿で他者と交流したり、イベントや仕事、学びの場に自由に参加したりすることが可能になります。
ビジネスチャンスの拡大
メタバースを活用することで、新たな市場の開拓やこれまで難しかった顧客層へのアプローチも可能になります。実際に、仮想空間上での店舗展開や広告の活用、イベントの開催といった取り組みを通じて、販路拡大や新規サービスの開発を図る企業も増加しています。
さらに、メタバースはグローバル展開を容易にする点でも注目されています。物理的な拠点を持たなくても、世界中のユーザーに対してサービスを提供できることは、メタバースならではの大きな魅力の一つといえるでしょう。
メタバースのデメリット・課題
メタバース活用におけるデメリットや課題は以下の通りです。
- 技術力やコストの負担
- 依存・過剰没入のリスク
- セキュリティ・プライバシーの問題
- 法整備の遅れ
それぞれについて詳しく確認していきましょう。
技術力やコストの負担
メタバースの構築・運用には高度な技術力と大きな初期投資が必要になります。具体的には、高性能なサーバーや3Dグラフィックス、AI、ネットワークインフラ、VRデバイスなどの整備が不可欠であり、中小企業や個人にとっては参入障壁が高いのが現状です。
また、快適な体験を得るためには、ユーザー側にも高性能なデバイス(PC、スマートフォン、VR機器など)や安定した通信環境等、一定の設備投資が求められます。
さらに、開発後もシステムの維持管理、アップデート、セキュリティ対策といった継続的なコストが発生します。このような技術的・経済的負担が、メタバースの普及スピードや参加ユーザーの多様性を制限する一因となっています。
依存・過剰没入のリスク
メタバースは高い没入感をもたらすため、現実世界との境界が曖昧になりやすく、依存や過剰な没入を招くリスクもはらんでいます。特に若年層においては、長時間の利用が学業や生活リズム、人間関係に悪影響を及ぼすケースもあり、社会的な孤立や精神的な問題に発展する可能性も懸念されています。また、ゲームやSNSと同様に中毒性を持ちやすいため、過度な依存に陥りやすい点も注意が必要です。
メタバースを健全かつ快適に利用するためには、利用時間や目的の管理、ユーザー教育や、保護者・教育機関の見守りなどの対策が不可欠といえます。
セキュリティ・プライバシーの問題
メタバースでは、個人の行動や発言、購入履歴やアバター情報といった、多くのデータが収集・利用されています。そのため、プライバシー保護や情報セキュリティが重大な課題となっています。
特に、収集されたデータが第三者に渡るリスクや、不正アクセス・詐欺などのトラブルが懸念されています。実際に、NFTや仮想通貨をめぐる詐欺や資産流出などの被害も発生しており、ユーザーが安心して利用できる環境づくりが急務となっています。
法整備の遅れ
メタバース技術が急速に進化する一方、それに対応する法律や規制は整備が追いついていないのが現状です。
たとえば、アバター同士のトラブルやハラスメント、仮想空間内での詐欺行為、デジタル資産の所有権、課税ルール、知的財産権の保護など、現実社会で問題となる行為がメタバースでも起こり得ます。しかし、これらに対応する明確なルールや法的枠組みが整っていないため、ユーザーが被害に遭っても法的救済を受けにくいという問題があります。
また、メタバースは国境を越えた活動が前提となるため、国際的な法整備やガイドラインの策定も求められています。
おすすめのメタバースプラットフォーム
メタバースの技術進化や普及とともに、新しいメタバースプラットフォームも次々と誕生しています。ここからは、今注目されているメタバースプラットフォームの特徴やサービス内容について、詳しく解説します。
XR CLOUD
XR CLOUDは、兵庫県に本社を置くmonoAI technology(モノアイテクノロジー)株式会社が開発・提供するバーチャル空間プラットフォームです。同社は、ゲーム業界向けのエンジン開発で培った自社技術を活用し、10万人以上の大規模同時接続を可能とするバーチャル空間開発ソリューションを提供しています。
XR CLOUDは、スマートフォン、PC、タブレット、VRデバイスといった多様なデバイスに対応しており、ユーザーは場所や端末を問わず手軽に仮想空間へアクセスすることが可能です。また、Unity向けの開発キット(SDK)も提供されており、企業やクリエイターが独自のアバターやワールドを簡単に構築・導入できる柔軟性も備えています。
特に法人向けでは、バーチャル空間を利用した製品展示、企業説明会、研修プログラムなどに活用されており、リアル開催では難しい大規模かつ遠隔地同士の同時参加を実現しています。さらに、アバターによる自然なコミュニケーションやデータの可視化、参加者の行動解析といった機能も強化されており、メタバースならではの価値をビジネスに取り込む動きが広がっています。
VRChat
VRChatは、米国の企業VRChat Inc.が開発・運営を行うソーシャルVRプラットフォームです。ユーザーが自作のアバターやワールド(空間)を持ち寄り、自由に交流できることを大きな特徴としており、個性的で多様な空間が日々生み出されています。
VRChatは、フルVR機器に対応しているだけでなく、デスクトップPCからの参加も可能で、初心者から上級者まで幅広い層のユーザーがアクセスできる環境が整っています。アバターの表情や手の動きがリアルタイムに反映されることで、実際にその場にいるかのような臨場感あるコミュニケーションが実現でき、言語や国境を越えた交流の場としても高く評価されています。
近年では、バーチャルライブ、オンラインセミナー、ファンイベントといった用途でも活用されており、単なる遊びの場を超えて、創作、教育、ビジネスの領域にも展開が広がっています。
oVice
oVice(オヴィス)は、石川県七尾市に本社を置くoVice株式会社が開発・提供する2Dベースのバーチャルオフィスプラットフォームです。
リモートワーク環境におけるコミュニケーションの円滑化やオンライン会議の効率化を主な目的としており、アバターを使って仮想空間上を自由に移動し、他のユーザーと近づくだけで自動的に音声通話が開始される仕組みを採用しています。雑談やちょっとした声かけなど、企業内の偶発的なコミュニケーションを再現できることから、国内外の多くの企業や団体で導入されています。
ブラウザベースで動作し、特別なソフトウェアのインストールや重いVR機器を必要としないため、導入・利用のハードルが低い点も大きなメリットです。また、オフィスのレイアウトやデザインを自由にカスタマイズできるため、企業のブランドイメージや業務スタイルに合わせた空間構築が可能な点も、oViceが高く評価されているポイントとなっています。
Mesh for Microsoft Teams
Mesh for Microsoft Teamsは、Microsoft社が提供する業務向けメタバース機能です。チームの一体感やエンゲージメントの向上を目的に開発された機能で、Teamsの会議機能に3Dアバターやバーチャル空間を統合することで、よりリアルに近いコミュニケーションを実現しています。
ユーザーは、自身のアバターで仮想空間内を移動しながら会話が可能で、焚き火を囲んだラウンジやカジュアルなミーティングルーム、フォーマルな会議スペースなど、目的に応じた多様なバーチャル空間を選択できます。
また、空間オーディオ技術により、距離に応じた音声の聞こえ方が再現されているのも大きな特徴です。この機能により、実際に同じ場所にいるような臨場感や高い没入感が得られます。
将来的には、Microsoft AzureやHololensとの連携も視野に入れており、ビジネス現場におけるメタバース活用を本格的に推進するプラットフォームとして期待されています。
Horizon Workrooms
Horizon Workroomsは、Meta社(旧Facebook社)が開発したビジネス向けVR会議プラットフォームです。主にMeta QuestシリーズのVRヘッドセットを利用し、仮想空間内でアバターを通して、ミーティングや共同作業が行えます。
Horizon Workroomsでは、空間オーディオ技術により、声の方向や距離感がリアルに再現されており、対面のような自然な会話が行えます。また、バーチャルホワイトボードやPC画面共有機能により、プレゼンやブレインストーミングなどがスムーズに行える点も魅力のひとつです。
Zoomとの連携も可能で、VRデバイスを持たないユーザーでも参加できるため、リモートワーク時代におけるチームの連携や創造的なコラボレーションを支援するツールとして注目されています。
REV WORLDS
REV WORLDS(レヴ ワールズ)は、株式会社三越伊勢丹が2021年3月に提供を開始したスマートフォン向けのメタバースアプリです。同アプリでは、JR新宿駅東口エリアや伊勢丹新宿店を再現した仮想都市空間で、ユーザーがアバターを通じて街歩きやショッピング、イベント参加などを楽しめます。
アバターは約130種類の髪型や顔、衣装などを組み合わせて自由にカスタマイズ可能で、チャットやエモート機能を使って他のユーザーとのコミュニケーションも活発に行えます。また、仮想伊勢丹新宿店では、3Dモデルで商品を閲覧し、気に入った商品をそのままオンラインストアで購入することも可能です。
開発には、三越伊勢丹と外部企業が共同で取り組んでおり、CG制作やシステム実装などを通じて、リアルな仮想都市体験を提供しています。また、博報堂DYメディアパートナーズの「hakuhodo-XR」プロジェクトとも連携し、バーチャル空間における新しい広告体験の設計や配信システムの開発も進められています。
Virbela(バーベラ)
Virbela(バーベラ)は、米国のeXp World Technologies, LLC.が開発したビジネス・教育向けのメタバースプラットフォームです。ユーザーがアバターを通して仮想空間に参加し、会議や研修、イベント、教育などをリアルに近い形で体験できます。
プラットフォーム内には、会議室、講堂、展示会場、屋外キャンパスなど、多様な空間が用意されており、アバターや環境のデザインを自社のブランディングに合わせてカスタマイズ可能です。さらに、特別なVR機器がなくてもPCからアクセス可能な点や、大規模な同時接続時でも安定した運用が可能な点も、Virbelaが評価されているポイントです。
日本では、株式会社ガイアリンクが公式販売代理店として、サービス展開を行っており、教育機関や企業の研修、国際会議、展示会など、幅広い分野で活用が進んでいます。
まとめ
メタバースは、私たちの暮らしや働き方に大きな影響を与える可能性のある技術です。すでにゲームやビジネス、ショッピング、エンターテインメントなど、多岐にわたる分野で活用されており、今後さらに進化していくことが期待されています。
一方で、コストやセキュリティリスク、依存や過剰没入など、解決すべき課題も少なくありません。誰もが安心してメタバースへ参加するためには、技術進化とともに、法や規制の整備、モラル教育を進めることが重要です。