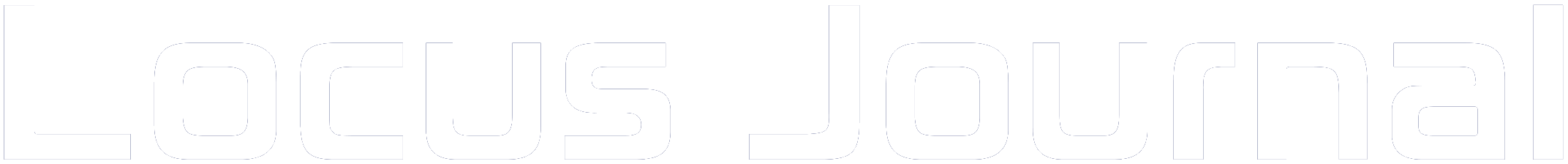近年、メタバースの活用がビジネスの現場でも急速に注目を集めています。これまでゲームやエンタメ領域を中心に広がっていた技術が、今では販売促進、採用活動、教育研修、製造現場など、さまざまなシーンで実用化され始めています。
しかし、メタバースという言葉は耳にしたことがあるけれど、実際にどう活用されているのかは知らない、本当に効果があるのかわからないと感じている方も多いかもしれません。
本記事では、メタバースの基本的な概念から、注目される理由、ビジネス導入のメリット、デメリットについて紹介します。あわせて、具体的なビジネス活用の事例についても紹介しますので、これから導入を検討したい企業や、情報収集を進めたい方はぜひ参考にしてください。
メタバースとは
メタバースとは、インターネット上に構築された3次元の仮想空間で、ユーザーがアバターと呼ばれる分身を使って他者と交流したり、買い物やゲーム、イベント、仕事など多様な活動を行ったりできる次世代のデジタルプラットフォームです。
現実を超えた「もう一つの社会」として注目されており、近年では、エンタメ領域だけにとどまらず、教育、医療、ビジネスの現場でも活用が進んでいます。さらに、NFTやブロックチェーン、AIといった先端技術との融合により、単なる仮想空間にとどまらず、経済活動や新しい顧客体験を生み出す場としても進化し続けています。
メタバースとよく混同されがちなのが「VR(仮想現実)」です。VRは主に視覚や聴覚を通じて仮想空間に没入するための体験技術であり、専用のゴーグルやヘッドセットを必要とします。一方で、メタバースはそのVR技術を活用する「場」や「仕組み」そのものを指しており、VRを含むより広範な概念を指します。
つまり、VRはメタバースを体験するための手段の一つであり、両者は密接に関係しているものの、役割や目的が異なるといえます。
関連記事:メタバースとは?VRとの違いや活用分野など基本から徹底解説!
メタバースが注目される理由
メタバースが注目される理由は、以下の点が挙げられます。
- 市場規模の大きさ
- 通信技術・VR技術の発展
- 大手企業の参入
- NFTとの親和性の高さ
- オンラインコミュニケーションの進化
それぞれのポイントについて詳しく確認していきましょう。
市場規模の大きさ
メタバース市場は急速な成長を遂げており、今後、数十兆円から数百兆円規模に達すると予測されています。
近年では、ゲームやエンタメ分野に限らず、教育、医療、不動産、製造などにもメタバースの活用が広がっており、バーチャルな空間での販売・研修・交流がビジネスとして成立しつつあります。
さらに、NFTや仮想通貨といったデジタル資産の普及により、個人・企業・行政がメタバース内で独自の経済圏を築く動きも活発化しています。
このように、メタバースは単なる仮想空間にとどまらず、新たな産業基盤としての役割を担いつつあります。業種や業態を問わず参入する企業も増加しており、バーチャル上での経済活動が現実のビジネスと結びつくことで、新しい市場価値を生み出しています。
通信技術・VR技術の発展
メタバースの発展は、通信インフラや、VR・AR技術の進化に大きく支えられています。特に、5GやWi-Fi 6といった高速・大容量・低遅延の通信技術の普及により、仮想空間内でもリアルタイムで映像や音声のやり取りが可能になった点は、メタバースの発展に大きく寄与したといえます。
また、VRゴーグルやARグラスといった関連デバイスの高性能化と低価格化も、メタバースのビジネス活用を後押しする重要な要因となっています。これまでメタバースの導入には、コスト面と技術面の両方で大きなハードルがありました。しかし近年、より軽量で操作性に優れた製品が手頃な価格で入手可能となり、企業が試験的にメタバースを導入しやすい環境が整いつつあります。
大手企業の参入
世界的な大手企業が次々とメタバース分野に参入していることは、メタバースの信頼性や注目度を高める大きな要因となっています。
とりわけ、2021年に米・Facebook社が社名を「Meta」に変更し、メタバースを中核事業に位置づけたことは世界に大きな衝撃を与えました。実際にMeta社は、数千億円規模の投資を行い、自社プラットフォーム「Horizon Worlds」の開発を進めています。これに続き、Microsoftは「Teams」と連携したビジネス向けメタバースの構築を進めており、Google、Apple、TencentなどのIT大手も関連技術やプラットフォームの開発に積極的に取り組んでいます。
日本国内でも、サイバーエージェントやグリーといったIT系企業のみならず、ソニー、トヨタ、NTT、日産、楽天など、多様な業界業種の大手企業が参入を表明しています。こうした企業の動きは、技術基盤やルール整備を後押しするだけでなく、市場全体の信頼性や安定性を高め、ユーザーや投資家の参入も加速させています。
さらに、業界を横断した連携や実証実験も各地で活発に行われており、中小企業やスタートアップにとってもメタバース市場へのアクセスが現実的な選択肢となりつつあります。
NFTとの親和性の高さ
NFT(非代替性トークン)は、「Non-Fungible Token」の略称で、代替不可能な唯一性を持つデジタル資産の所有や真正性を証明する技術を指します。ブロックチェーンによって所有権や取引履歴が記録されるため、偽造や改ざんが困難であり、デジタルデータにも現実のモノと同様の価値が付与できる点が大きな特徴です。
メタバースとの親和性も高く、アバターの衣装や装飾アイテム、土地や建物などのバーチャル不動産、デジタルアート作品など、仮想空間内のあらゆるコンテンツがNFTとして管理・取引できます。
この仕組みを活用することで、企業は、限定商品の販売や会員特典の提供、ブランドアイテムの資産化といった新しい収益モデルやマーケティング手法を実現できます。将来的に、NFTが複数のメタバースプラットフォームをまたいで利用できるようになれば、共通経済圏が広がり、ユーザーの回遊性とブランドの接点が飛躍的に増加することも期待できます。
オンラインコミュニケーションの進化
コロナ禍により対面での交流が制限されたことを契機に、非接触・非対面でも人とつながれる新しいコミュニケーション手段への関心が急速に高まりました。その中で、アバターを介して仮想空間で交流できるメタバースは、従来のビデオ通話やチャットとは異なる、没入感と臨場感に優れた体験を提供する手段として多くの注目を集めています。
メタバース内では、アバターの動きや視線、表情、ジェスチャーといった非言語的な要素も共有できるため、よりリアルに近いコミュニケーションが可能になります。これにより、会議、研修、面接、授業などで「同じ空間を共有する」感覚が生まれ、単なる情報伝達にとどまらない一体感や信頼関係の醸成にもつながります。
メタバースをビジネスで活用するメリット
ビジネス領域においてメタバースを活用するメリットは、以下の通りです。
- 新しい顧客接点・体験の提供
- 販路の拡大と収益源の多様化
- 効果的な求人・採用活動の実現
- リモートワーク・研修の高度化
- コスト効率の改善
- データ収集とマーケティング活用
それぞれの点について詳しく確認していきましょう。
新しい顧客接点・体験の提供
メタバースを活用すれば、従来のECサイトや実店舗とは異なる没入感とインタラクティブ性を備えた新しい体験を顧客へ提供できます。たとえば、アバターによる接客や仮想空間での試着・試用、空間演出などを通して、ユーザーの記憶に残る強い印象を与えられます。
イベントやキャンペーンも場所や時間の制約を受けずに開催できるため、海外市場や若年層など、これまでリーチできなかった顧客層へのアクセスも可能になります。SNSと連携することで拡散効果も期待できるため、話題づくりの場や新しいマーケティングの形としての活用も広がっています。
販路の拡大と収益源の多様化
メタバースは、企業にとって従来の販売チャネルとは異なる新たな収益機会を生み出す場として注目されています。たとえば、バーチャル空間上に自社のストアやショールームを展開すれば、物理的な制限を受けることなくグローバルに商品・サービスを提供できます。
また、NFTを活用したデジタルアイテムの販売や、限定イベントでの課金モデルなど、新しいマネタイズ手法も可能です。リアルな製品と連動した販促施策や、仮想空間限定のプロモーション展開など、収益源多様化に貢献する有力なツールとしてメタバースを活用する企業も増えつつあります。
効果的な求人・採用活動の実現
メタバースの活用は、企業の採用活動にも新たな可能性をもたらします。たとえば、仮想空間上で会社説明会や職場体験、社員との座談会、オフィスツアーなどを開催することで、求職者に企業文化や職場の雰囲気を、より直感的かつリアルに伝えることが可能です。
物理的な移動が不要なため、遠方の学生や多忙な転職希望者、海外在住の人材にもアプローチしやすく、応募者の母数拡大にもつながります。また、アバターを通じたコミュニケーションは緊張を和らげ、対面では得られにくいフラットな対話の促進にも役立ちます。
ダイバーシティやインクルージョンが重視される現代において、メタバースは多様な人材との接点を生み出す有効な採用手段のひとつといえるでしょう。
リモートワーク・研修の高度化
働き方改革の推進や新型コロナウィルスの感染拡大などきっかけに、リモートワークやハイブリッド勤務が普及し、企業の働き方は多様化しています。このような中で、メタバースは、従来のリモートワークやオンライン研修の限界を補い、よりリアルに近い業務体験や学習環境を提供できる手段として注目されています。
たとえば、仮想オフィスを活用すれば、アバターを介して上司や同僚と気軽に声を掛け合えて、雑談や偶発的なコミュニケーションも生まれやすくなります。テキスト中心のチャットやビデオ会議等では得にくい一体感やつながりが生まれやすい点は、メタバースの特徴といえるでしょう。
また、研修においては、実際の作業環境や業務プロセスを仮想空間内で再現することで、現場に近い体験型のトレーニングが可能になります。マニュアルに頼るだけでなく、実践的なスキルを効率的に習得できるため、製造業や医療の分野でも実用化が進んでいます。
コスト効率の改善
メタバースを活用することで、企業の業務運営に必要なコストの削減が期待できます。たとえば、社内会議や採用イベント、商品展示会などを仮想空間で実施すれば、会場の設営費や交通費、宿泊費といった物理的なコストを大幅に削減できます。加えて、時間的なロスも減らせるため、業務全体の生産性向上も見込めます。
また、メタバース内に設計された研修コンテンツやバーチャルショールームなどは、一度構築すれば何度でも再利用できるため、運用コストの削減も可能です。リアルと比べてスピーディに環境を変更・調整できる柔軟性もあり、効率性の高い業務推進の実現にも貢献します。
データ収集とマーケティング活用
メタバースは、ユーザーの行動をリアルタイムで可視化できるため、データ収集やマーケティングへの活用にも優れています。たとえば、バーチャルストア内での動線や滞在時間、興味を示した商品やエリアなどを分析することで、顧客の行動特性やニーズを詳細に把握できます。
さらに、AIと連携することで、個々のユーザーに合わせたレコメンドや広告表示も可能になります。これにより、より高精度なターゲティングや最適なタイミングでの情報提供が実現し、プロモーション効果を最大化できます。
アンケートやインタラクションを通じたフィードバック収集も自然に行えるため、UXの向上やプロモーション戦略の強化にもつながります。
メタバースをビジネスで活用するデメリット・課題
メタバースをビジネスに活用することで、多くのメリットが期待できます。しかし、一方で、導入・運用の際には、以下のように注意すべき課題も存在します。
- 初期投資・運用コストが高い
- 技術リスク・運用ノウハウ不足
- 利用者層の限界
- セキュリティ・法規制リスク
- ブランディングリスク
それぞれの点について、具体的にどのように注意すべきなのか、確認していきましょう。
初期投資・運用コストが高い
高品質なメタバース空間を構築するには、3Dデザイン、エンジニアリング、ネットワーク構築、UX設計など多様な技術が必要です。そのため、導入規模によっては、初期費用が数百万円~数千万円にのぼる可能性もあります。
加えて、運用後もコンテンツの更新やセキュリティ対策、ユーザーサポートなど継続的なコストが発生します。そのため、収益化までに時間がかかるケースも少なくありません。
中小企業やスタートアップ企業でメタバースの導入を行う場合は、外部サービスや既存プラットフォームの活用など、スモールスタートでの開始を検討するのが現実的といえるでしょう。
技術リスク・運用ノウハウ不足
メタバースに関連する技術は、まだ発展途上な部分が多く、互換性のなさ、不安定さ、バグの多さなど、さまざまな問題が発生するリスクがあります。そのため、仮想空間を安定的に運用するには、専門的な知識や経験、高い技術力が求められます。
しかし、多くの企業では、そのような人材が社内におらず、開発や管理を外部ベンダーに依存せざるを得ないのが現状です。その結果、導入後に発生する不具合や仕様変更への対応が遅れ、ユーザー体験の低下やシステム全体の運用に支障をきたすリスクがあります。さらに、外部ベンダーとの連携が十分でなかった場合、改善の優先順位や対応スピードにズレが生じ、トラブルが長期化する恐れもあります。
メタバースの導入と安定運用を実現するためには、社内教育や外部との連携を通じて、徐々に内製化を進めていくことも重要です。
利用者層の限界
メタバースはデジタルリテラシーの高い若年層やゲーム慣れしたユーザーを中心に高い支持を得ていますが、まだ誰もが日常的に使える技術であるとはいえないのが現状です。
特に、中高年層やITに不慣れな層には、操作やアカウント作成、アバター設定などのハードルが高く、参加を敬遠されがちです。また、VRゴーグルなどの専用デバイスが必要なケースでは、コスト面や使い方への不安から利用を避ける人も存在します。
そのため、企業がメタバース上でイベントやサービスを展開しても、想定したターゲット層が十分に集まらないケースや、または期待した反応が得られないケースも少なくありません。より幅広い層への普及には、UI/UXの改善や教育・サポート体制の整備が不可欠です。
セキュリティ・法規制リスク
メタバース空間では、個人情報や行動データ、仮想通貨などの重要なデジタル資産が多く扱われるため、セキュリティ上のリスクが避けられません。アカウントの乗っ取りや不正アクセス、フィッシング詐欺などの脅威に加えて、ユーザー同士のトラブルや誹謗中傷も現実の問題として起きています。
また、国や地域によって異なる法規制が適用されるため、商取引や表現内容に関するトラブルが発生しやすい点も注意が必要です。
企業がサービス提供側になる場合は、利用規約の整備や法務チェック、セキュリティ対策ソフトの導入など、多方面での備えが必要です。ユーザーとの信頼関係を築くためにも、透明性と安全性を担保した運用が求められます。
ブランディングリスク
メタバースでは、ユーザーの行動を完全に制御することが難しいため、企業が意図しない形でブランドイメージに悪影響を及ぼすリスクがあります。
たとえば、企業が提供した仮想空間内で不適切な言動やトラブルが発生した場合、それが炎上やSNSでの拡散につながり、企業の責任や信用問題につながる可能性があります。また、仮想空間の設計やコンテンツの質がブランドと合致していない場合、ユーザーに違和感や不信感を与えるリスクもあります。
メタバース活用にあたっては、長期的なブランド戦略との整合性や、運営側の監視体制や品質管理、ユーザーサポート体制を事前に明確にしておくことが重要です。
メタバースのビジネスでの活用事例10選
前述したとおり、メタバースは業界業種を問わず、さまざまな企業で活用が進んでいます。ここからは、メタバースがビジネスシーンでどのように活用されているか、具体的な事例を紹介していきます。
イベント・交流会
株式会社サンリオと株式会社サンリオエンターテイメントは、2023年1月にメタバースを活用したバーチャル音楽フェスティバル「SANRIO Virtual Festival 2023」を開催しました。VRChat上に再現されたサンリオの仮想空間には、ハローキティをはじめとした人気キャラクターが登場し、アーティストとのライブパフォーマンスやバーチャルグリーティング、限定アイテムの販売などが展開されました。
ユーザーはアバターを使って自由に空間を移動し、ステージを観覧したり、仲間と写真を撮ったりと、リアルでは味わえない体験を楽しめました。こうした取り組みは、国内外のファンから高い評価を受け、メタバースを活用したIPビジネスの成功事例となっています。
参考記事:「SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland」開催レポート
ショールームの設置
日産自動車は2021年に、メタバース空間を活用したバーチャルショールーム「VR NISSAN CROSSING」を公開しました。これは、東京・銀座に実在するブランド発信拠点「NISSAN CROSSING」を、VRChat上に再現したものです。
ユーザーはアバターで仮想空間を自由に移動しながら、展示車両を360度好きな方向から閲覧でき、車の外観・内装・デザインの魅力を直感的に体感できます。また、特定のイベント時には、スタッフ(アバター)との会話機能や限定配信なども提供され、双方向の体験型コンテンツとして設計されています。
この取り組みは、リアル店舗ではリーチしにくい地方在住者や若年層への情報発信にも効果があり、メタバースならではの柔軟なアクセス性と没入感を活かした新しい顧客体験として注目されています。導入後は国内外からのユーザーが集まり、ブランド認知の向上と商品理解の促進に貢献しています。
住宅展示場・モデルハウス
大和ハウス工業は、2022年4月に業界初となるメタバース住宅展示場を公開しました。ユーザーはアバターを使って仮想空間を移動し、モデルハウスの内装や間取りをリアルタイムで見学できます。屋根の上からの目線や、子ども・ペットの目線への切り替え、紙や床材の色・素材、インテリアの変更も行えるなど、メタバースならではの体験ができるのが特徴です。
見学中に担当者とアバターで通じて会話もできるため、遠方や多忙で実際の住宅展示場に足を運べない顧客からも好評を得ています。
メタバース住宅展示場は、営業活動の非対面化と顧客満足の向上を同時に実現する新たな住宅提案の形として、注目されています。
参考記事:メタバース見学会ならLiveStyle PARTNERへ
バーチャルオフィス・バーチャル会議室
米・Meta社が提供する「Horizon Workrooms」は、バーチャルオフィスやバーチャル会議室機能を備えたメタバースプラットフォームです。ユーザーはアバターとしてバーチャル会議室に参加し、実際のデスクやキーボードを仮想空間内に再現しながら、プレゼンテーションやディスカッションを行えます。
同サービスの大きな特徴には、空間オーディオによる自然な会話体験と、仮想ホワイトボードや資料共有機能など、リアルな会議と同様の臨場感と機能性を備えている点が挙げられます。また、アバターを通じて参加者の動きや表情が視覚的に伝わるため、オンライン会議で失われがちな非言語コミュニケーションが補完できる点もポイントです。
基本的にはVRヘッドセット(Meta Quest)を利用して仮想空間に参加しますが、PCからのアクセスにも対応しており、デバイスに制限されずに活用できる点も魅力といえます。さらに、Zoomとの連携機能も備えているため、VRと従来のオンライン会議を組み合わせたハイブリッドな会議体制も構築できます。
こうした設計により、「Horizon Workrooms」は、リモートワークにおける物理的な距離や一体感の希薄化といった課題の解消を図る、次世代のコミュニケーションツールとなりつつあります。
教育・トレーニング
福岡工業大学生命環境化学科の赤木研究室では、メタバースを活用した実験的な教育空間「Akagi Lab」を構築し、学生の学びに取り入れています。仮想空間上にアバターとして参加することで、学生は教室とは異なる自由な環境でディスカッションやプレゼンテーションに取り組めます。
中でも特徴的なのは、アメリカの夜景や宇宙を模した空間演出や、細胞内部を3Dで探索できる仮想「細胞空間」の導入です。これにより、視覚的に理解しにくい内容も、体験的に学べるようになっています。
また、発話量や移動距離などの行動ログや、脳波計測を通じて学習効果を定量的に分析する試みも進められており、教育の質の向上とともに、対面授業では得られにくい没入感や心理的安全性の確保にもつながっています。
参考記事:メタバースで「学び」は変わる!?授業導入を試行開始
バーチャルストア・バーチャルマーケット
HIKKYが主催する「バーチャルマーケット(Vket)」は、メタバース空間上で展開される世界最大級の商業イベントです。毎年夏と冬に開催され、累計来場者は100万人を超えるなど、メタバース領域における代表的な成功事例のひとつとされています。
ユーザーはVRヘッドセットのほか、PCやスマートフォンからもアクセスが可能。アバターで仮想会場を自由に歩き回りながら、3Dアイテムやリアル商品の購入、バーチャル接客、ライブ体験などを通じて、メタバースならではの没入型ショッピング体験を楽しめます。
会場には企業ブースも設けられており、ファッション、食品、自動車など幅広い業種が参加しています。大丸松坂屋やBEAMSといった大手企業もメタバース上に出店しており、新たな販売チャネルの可能性を広げています。
参考記事:VIRTUAL MARKET
製造業
川崎重工業株式会社は、米・Microsoft社と連携し、製造現場の全工程を仮想空間上で再現するインダストリアルメタバースの構築に取り組んでいます。
この取り組みでは、製造現場の可視化と遠隔支援の実現に向けて、クラウド/IoTプラットフォーム(Azure IoT、Azure Percept)やMRヘッドセット(HoloLens)、デジタルツイン技術(Azure Digital Twins)などのMicrosoft製品が活用されています。これにより、予兆保全や故障対応が遠隔で可能となり、複数拠点の技術者がVRやMRでリアルタイムに連携しながらトラブルシュートを行えるようになりました。
さらに、Microsoft社の開催する「Microsoft Build 2022」では、川崎重工業によるロボット操作の遠隔支援や、工場全体の共同作業プラットフォーム構築の取り組みが紹介され、製造業におけるデジタル変革の象徴的な取り組みとして評価されています。
参考記事:産業での活用が進むメタバース: 設計、開発から試験まですべての工程を仮想空間上で実行できるコラボレーション環境を目指す、川崎重工の取り組み
旅行
2023年1月、広島県呉市の特別養護老人ホーム「仁方」で、VR機器を活用した疑似旅行体験会が開催されました。
参加者はVRヘッドセットを装着し、仮想空間内で瀬戸内海のクルージングや厳島神社、呉港、商店街などの観光地を360度の映像と音響で体験しました。その場にいるかのような臨場感あふれる旅の疑似体験により、参加者からは「実際に旅行した気分になった」といった感想も寄せられました。
この試みは、高齢者が体力的な制約を超えて旅行を楽しめるだけでなく、気分転換や心のリフレッシュ、精神的な活力の向上にもつながると期待されています。また、米・Meta社のVR技術との連携も図られており、福祉とメタバースの融合による新たなケアのあり方を示す事例として注目されています。
参考記事:高齢者がVRで“旅行”、障害者にはメタバースで就労支援も 福祉にデジタル導入…「VR旅行」は米メタとも連携
PR
大阪府泉佐野市は、2022年12月に開催された「バーチャルマーケット2022 Winter」に出展し、メタバースを活用したふるさと納税のPRを行いました。
ブース内では、泉佐野市の人気返礼品である牛肉やお米、泉州タオル、地元のクラフトビールなどを3Dで展示し、来場したユーザーが自由に見て楽しめるようになっていました。また、市の公式キャラクター「イヌナキン」や「ゆるナキン」も登場し、ロデオ体験ができる仕掛けなど、遊び心のある演出で地域の魅力を訴求しました。
さらに、その場で寄付手続きができるよう、展示ブース内にふるさと納税サイトへの導線を用意。スマートフォンやPCからもアクセスできるようにしたことで、幅広いユーザーへのアプローチにも成功しました。
この取り組みは、自治体がメタバースを活用してPRと寄付促進を同時に図った事例として注目されており、地域振興の新たな形を示す試みとして評価されています。
参考記事:泉佐野市がバーチャルマーケット2022 Winterに出展決定!!メタバースの中でふるさと納税の返礼品を選べるブースを出展します
ゲーム
Epic Gamesが提供するオンラインゲーム「フォートナイト」は、世界中で4億人以上の登録ユーザーを持つ人気タイトルで、メタバース型ゲームの先駆けとして知られています。
フォートナイトでは、通常のバトルロイヤル形式のプレイに加えて、ユーザーが独自のワールドやゲーム空間を作成できる「フォートナイト・クリエイティブ」や「Unreal Editor for Fortnite(UEFN)」といった機能が提供されています。
さらに、米津玄師さんやトラヴィス・スコット、アリアナ・グランデといった国内外の有名アーティストによるバーチャルライブイベントも開催されています。イベントには、数千万人規模のユーザーが参加しており、仮想空間だからこそ味わえる臨場感と一体感が提供されています。
フォートナイトは、遊ぶ・つながる・創るという要素を合わせ持つソーシャル型のメタバースゲームとして進化を続けており、エンタメとテクノロジーを掛け合わせた、仮想空間の新しいスタンダードを築きつつあります。
参考記事:メタバースの本命と呼ばれる、フォートナイトとEpic Gamesの凄さ
まとめ
新しい顧客体験の提供や販路拡大、コスト効率の改善などを目的に、メタバースをビジネスに活用する動きが広がっています。住宅、製造、自治体、旅行など、メタバースを実際に導入し、成果を上げる事例も近年、増加しています。
一方で、導入にはコストや技術的なハードル、運用面での課題も伴います。そのため、自社で導入を検討する際には、目的やターゲットに応じた活用方法を見極め、段階的に取り組むことが重要です。
今後もテクノロジーの進化とともに、メタバースはさらに新しい価値や体験を生み出していくと考えられます。メタバースの動向や導入企業の事例を参考にしながら、自社にとって最適な関わり方を見つけていくことが、メタバース活用の成功のカギとなるでしょう。