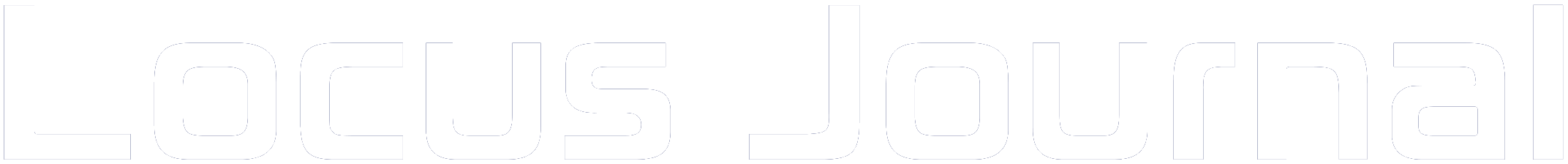企業が保有する建物や設備、機械、車両、ソフトウェアといった固定資産は、長期にわたって事業を支える重要な存在です。これらの固定資産を適切に管理することは、利益の最大化や予期せぬ損失の防止につながります。
本記事では、固定資産種類や、固定資産管理の必要性・メリット、具体的な管理方法や業務の流れについて、詳しく解説します。固定資産管理の知識を得たい人や、固定資産業務の見直しを検討している方はぜひ参考にしてみてください。
固定資産とは
固定資産とは、企業が事業を継続的に行うために長期保有する財産のことで、原則として1年以上の使用を目的とするものを指します。会計上は「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」の主に3種類に分類されます。
|
分類 |
概要 |
内容例 |
|
有形固定資産 |
物理的な形があり、企業の事業活動を支える基盤。管理や修繕の記録が必要。 |
土地、建物、機械、車両、工具、備品など |
|
無形固定資産 |
実体はないが、企業活動に有益な権利や資産。経営資源としての価値が高い。 |
特許権、商標権、著作権、ソフトウェアなど |
|
投資その他の資産 |
長期的な運用や戦略的保有を目的とした資産。リスクと収益のバランスを考慮する必要がある。 |
投資有価証券、長期貸付金など |
さらに、有形固定資産は、減価償却の要否により「減価償却資産」と「非減価償却資産」の2種類に分類されます。
|
分類 |
概要 |
内容例 |
|
減価償却資産 |
使用や経年によって価値が減少する資産。耐用年数に基づいて定期的に費用計上される。 |
建物、機械、車両、工具、備品など |
|
非減価償却資産 |
通常、価値が減少しないとされる資産。帳簿上の価値が維持される。 |
土地など |
固定資産管理とは
固定資産管理とは、企業が保有する固定資産について、その取得から設置・使用・減価償却・修繕・棚卸・廃棄に至るまでのライフサイクル全体を一貫して記録、管理する業務です。
会計処理のための減価償却や棚卸の基礎となるだけでなく、資産の所在や使用状況を把握するための基盤となる重要な業務で、特に資産数が多い企業では、効率的かつ正確な管理体制が求められます。
固定資産管理の業務内容と流れ
固定資産管理では、資産の取得から、最終的に廃棄、除却されるまで、段階に応じてさまざまな業務が発生します。ここでは、固定資産管理の主な業務の流れと、管理の際のポイントについて解説します。
1. 資産の取得・登録
新たに固定資産を購入・取得したら、まずは固定資産台帳に以下のような資産の情報を記録・登録します。
- 取得日
- 取得金額
- 勘定科目
- 耐用年数
- 減価償却方法
- 設置場所
- 管理部門
取得時の登録が不十分だと、後々の減価償却や棚卸に支障が出るため、初期登録には特に高い正確性が求められます。
2. 設置・使用状況の把握
取得した資産がどこに設置され、誰がどのような目的で使用しているかを把握しておくことも重要です。
部署の異動やレイアウト変更などに合わせて情報の見直し・更新を実施すれば、不要資産の発見や流用の防止、重複購入や資産の紛失の抑制につながります。
3. 減価償却の管理
減価償却とは、固定資産の取得費用を耐用年数に応じて分割し、費用として計上する会計処理です。企業は、各資産に設定された耐用年数や減価償却方法(定額法・定率法など)に基づき、毎期の償却額を算出し、帳簿上で処理していく必要があります。
計算間違いや計上漏れがあると、税務申告や財務諸表に大きな影響を与えるため、正確な台帳管理と定期的な確認が求められます。
4. 棚卸・実地調査
固定資産の実際の所在や状態を確認するために、定期的な棚卸や実地調査を行います。棚卸とは、帳簿と現物を突合し、資産の存在確認を行う業務を指します。目視やバーコード・QRコード・RFIDなどのツールを用いて、資産の所在や状態をチェックします。
不一致がある場合は、調査と修正を行い、情報の正確性を保ちます。
関連記事:「棚卸し」って何?気になる目的や作業方法を徹底解説!
5. 修繕・メンテナンス管理
資産の寿命を延ばし、稼働率を維持するためには、定期的なメンテナンスや修繕が欠かせません。
修理履歴や必要となった費用もあわせて記録しておくことで、次回の修繕計画や資産更新の判断材料になります。また、突発的な故障を防ぐ予防保全としても有効です。
6. 売却・除却・廃棄
使用しなくなった固定資産は、売却して資金化するか、不要資産として除却・廃棄を行います。これらの処理では、帳簿上の資産を整理し、売却益や損失を正しく計上することが重要です。
適切な管理を行えば、会計の正確性が確保され、遊休資産の圧縮や経営資源の有効活用にもつながります。
固定資産管理の必要性・メリット
固定資産管理の必要性およびメリットには主に以下の点が挙げられます。
- 財務・税務の正確性向上
- コスト削減
- リスクマネジメント
- 内部統制の強化
それぞれのポイントについて詳しく確認していきましょう。
財務・税務の正確性向上
固定資産管理の正確性は、財務諸表の信頼性に直結します。減価償却費や帳簿残高を正しく把握することで、決算の透明性が高まり、監査や税務調査への対応もスムーズになります。
管理する情報やデータが不正確であると、誤った会計処理や粉飾決算の疑いにつながる恐れがあるため、注意が必要です。
コスト削減
固定資産を適切に把握しておくことで、不要な資産の保有や重複購入を防ぎ、遊休資産を有効活用できます。
また、修繕費や保守契約の適正化など、継続的に資産管理を行うことで、間接的なコストの削減にもつながります。特に製造業など設備投資の多い業種では、大きな経費削減効果が期待できます。
リスクマネジメント
資産の紛失、盗難、破損、老朽化といったリスクは、企業活動に思わぬ損失を与えます。定期的な管理によってこれらのリスクを早期に把握・対処すれば、突発的な業務停止や損害を未然に防げます。
また、災害や事故の発生時でも固定資産台帳が整備されていれば、被害状況の把握や保険請求がスムーズに進みます。
内部統制の強化
固定資産管理は、内部統制やコンプライアンスの強化にもつながります。誰がどこでどの資産を使用しているのかを明確にすることで、不正使用や無断移動のリスクを減らし、結果として組織全体のガバナンス向上にも寄与します。
また、固定資産の管理記録が適切に整備されていれば、監査や税務調査の際にもスムーズに説明責任を果たせて、外部からの信頼確保にもつながります。
固定資産管理の方法:システム面
固定資産の管理は、企業規模や管理対象の資産数に応じて、さまざまな方法が選択できます。ここでは、Excelを使用した管理方法と固定資産管理システムを活用した管理方法について、それぞれ詳しく解説します。
Excelで管理する
Excelを活用すれば導入コスト不要で、気軽に固定資産管理を行えます。Excelは自由度が高いため、会社独自の管理項目や分類方法にも柔軟に対応できます。また、特別なトレーニングを行わなくても誰でも操作でき、すぐに運用を始められるのも大きなメリットといえるでしょう。
ただし、資産が増えると更新作業が煩雑になり、入力ミスや情報の重複・欠落のリスクも高まります。そのため、少数の固定資産を扱う場合や、固定資産管理システム導入前の一時的な運用には適していますが、長期的には管理負荷が増大しやすい方法ともいえます。
固定資産管理システムを活用する
一定以上の資産を抱える企業では、固定資産管理システムの活用が効果的です。システムを導入することで、資産の登録から減価償却の自動計算、台帳更新、棚卸結果の反映、修繕や除却まで一元的に管理できます。
また、クラウド型やオンプレミス型などから、自社の規模や業務形態に合わせて選択できるのも特徴です。さらに、ERPや会計システムと連携すれば、財務情報との整合性が自動で取れ、内部統制や監査対応も容易になります。
初期投資は必要ですが、業務効率の向上とデータの正確性、内部統制の強化といったメリットが得られるため、中長期的には費用対効果の高い選択肢となるでしょう。
関連記事:【徹底比較】固定管理システム15選!基本機能や選び方をわかりやすく解説!
固定資産管理の方法:認識方法
固定資産を正確に管理するには、システムだけでなく、現物資産をどう識別・認識するかも重要です。ここでは、「目視」「バーコード」「QRコード」「RFID」の4つの認識方法について紹介します。
目視
資産に貼付したラベルや管理番号を人の目で確認し、台帳やシステムに手入力する最も基本的な方法です。目視による認識方法の主なメリットや注意点、利用シーン例は以下の通りです。
【メリット】
- 特別な機器やシステムが不要なため、導入コストがかからない
- ラベル等の貼り付けだけですぐに運用を開始できるため、少数の資産管理や暫定運用に適している
- 管理ルールを柔軟に変更しやすい
【注意点】
- 作業者の経験や注意力に依存するため、ヒューマンエラーが発生しやすい
- 資産が増えると、棚卸や移動履歴の更新が負担になる
【利用シーン例】
- 小規模事業所での備品管理
- システム導入前の一時的な運用
バーコード
資産に貼り付けた一次元コードを専用のスキャナで読み取り、情報を収集する方法です。バーコードによる認識方法の主なメリットや注意点、利用シーン例は以下の通りです。
【メリット】
- 目視よりも高速かつ正確に資産を識別可能
- ハンディターミナルやスマートフォンアプリで簡単にスキャンできる
- ラベル印刷コストが低く、導入ハードルが低い
【注意点】
- 1つずつ読み取る必要があるため、大量資産の同時棚卸には不向き
- ラベルが汚れたり剥がれたりすると読み取りできないことがある
【利用シーン例】
- 数百~数千規模の備品管理、PC・OA機器の棚卸
関連記事:10分でバーコード・QRコード・RFIDを利用した在庫管理がわかる
QRコード
資産に貼り付けた二次元コードをスマートフォン等で読み取り、情報を収集する方法です。QRコードによる認識方法の主なメリットや注意点、利用シーン例は以下の通りです。
【メリット】
- バーコードに比べ格納できる情報量が多く、読み取り速度も速い
- スマートフォンで読み取り可能で、専用機器が不要なケースもある
- 資産の管理番号だけでなく、型番、取得日、管理部署などの情報を埋め込むことも可能
【注意点】
- バーコードと同様にラベルが汚れると読み取りに支障が出る
- 1つずつスキャンが必要なため、大規模資産の管理には時間がかかる
【利用シーン例】
- 社内備品の管理
- IT資産や貸与機器のトラッキング
RFID
RFID(Radio Frequency Identification)は、資産に貼付したICタグを無線通信によって非接触で読み取る先進的な方法です。RFIDによる認識方法の主なメリットや注意点、利用シーン例は以下の通りです。
【メリット】
- 一度に複数の資産をまとめてスキャンできるため、棚卸作業を大幅に効率化できる
- 見えない場所にある資産や段ボールなどに入ったままの資産でも読み取りが可能
- 棚卸精度が高く、ヒューマンエラーを削減できる
- 汚れに強い
【注意点】
- RFIDタグ、リーダーなど、導入コストが必要
- 金属や液体の影響で読み取り精度が低下するケースがある
【利用シーン例】
- 工場設備、倉庫内の大型資産の管理
- 全国に点在する拠点の資産管理
関連記事:RFIDで在庫・物品管理!?RFID x ロボットで棚卸しを無人化!
まとめ
固定資産管理は、企業の経営基盤を守り、財務の健全性や業務効率を支えるために欠かせない業務です。取得から廃棄までのライフサイクル全体を正確に管理することで、無駄なコストを抑え、リスクを軽減し、信頼性の高い財務情報を構築できます。
管理方法や資産の認識方法にはさまざまなものがあり、それぞれメリットや注意点が異なります。固定資産管理を効率的かつ正確に行うためには、企業規模や業種、自社の資産の種類や数に合わせて最適なツールや仕組みを導入することが重要です。