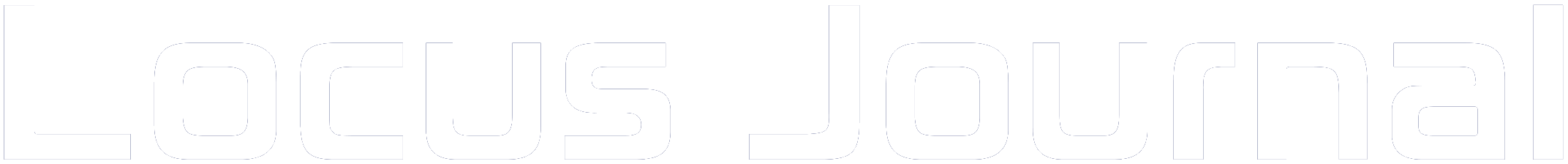市場競争の激化や人手不足が深刻な製造業において、効率化は喫緊に取り組むべき、重要な課題の一つであるといえます。しかし、効率化といってもどのように取り組めばいいかわからない、効率化に着手しているがうまく取り組みが進まないと感じている方も多いかもしれません。
今回は、製造業において効率化が求められる背景や、効率化を阻む要因、効率化を実現する具体的な方法について、詳しく解説します。
製造業における効率化とは
製造業における効率化とは、限られた資源や時間を最大限に活用し、生産性を向上させる取り組みを指します。具体的には、作業工程の見直しや自動化、在庫管理の最適化などを通じて無駄を省き、品質を維持しつつコスト削減を図ることを目的としています。
製造業を取り巻く環境が目まぐるしく変化している昨今では、企業の競争力を高め、持続的な成長を支える要素として、効率化は非常に重要なものであると考えられています。
製造業で効率化が求められる理由
製造業において効率化が求められる背景には、主に以下の2つの理由が挙げられます。
- 生産年齢人口の減少
- 国内外での競争激化
それぞれについて詳しく確認していきましょう。
生産年齢人口の減少
生産年齢人口とは、生産活動の中心となる15歳から64歳まで人口を指します。少子高齢化が進む日本では、1995年をピークに生産年齢人口の減少が続いています。総務省が発表した「情報通信白書(令和4年度版)」によると今後も生産年齢人口の減少は続き、2050年には5,275万人(2020年から29.2%減)になると予測されています。
生産年齢人口が減少すれば、労働力の確保が困難になり、多くの企業が人手不足に陥ります。とくに中小企業では労働力不足が深刻化します。また、熟練者の退職が進むことで、技術継承の問題も顕著になっています。
限られた人材で高い生産性を維持するためには、業務の標準化や自動化、デジタル技術などを用いた効率化が強く求められています。
国内外での競争激化
グローバル化の進展により、製造業は国内外の企業との競争にさらされています。とくに低コストで製品を提供する新興国企業との価格競争や、国内外企業との技術競争は激化しており、なにも対策をしなければ、市場から淘汰されるリスクも高くなります。
このような市場環境の中でコストや品質、納期などで優位性を保ち、高い競争力を維持するために、効率化は製造業が取り組むべき重要な課題の一つであるといえます。
効率化によって期待できるメリット
効率化を実現することで期待できるメリットには以下の通りです。
- 品質の安定
- コスト削減
- 利益の増大
それぞれの点について詳しく確認していきましょう。
品質の安定
効率化の一環として、作業工程の標準化や自動化を導入することで、製品の品質が安定します。人為的なミスが減少し、均一な品質の製品を提供できるため、顧客満足度の向上も見込めます。
また、製品品質が安定することで、トラブルやクレームなどイレギュラーな対応が減り、作業にかかる時間の短縮が可能になります。空いた時間を製品の研究・開発、若手従業員への技術やノウハウ継承に当てられるようになるため、企業の競争力強化や、後継者不足解消も期待できます。
コスト削減
効率化を実施し、無駄な作業や資源の浪費を省ければ、エネルギーコストや人件費など、さまざまなコストの削減が可能になります。
削減した費用を、従業員への投資や新たな設備への投資、業務効率化に役立つシステムやツールの導入に利用すれば、さらなる生産性向上や従業員満足度の向上にもつながります。
利益の増大
効率化によって、生産性の向上と、コスト削減が実現できれば、製品あたりの利益率の上昇が見込めます。
また、製品品質の安定によって、顧客満足度が向上すれば、リピーターの増加や新規顧客の獲得につながり、売上拡大も期待できます。
製造業で効率化が進まない原因
製造業の効率化を阻む要因として挙げられるのは以下の通りです。
- 人材不足
- 標準化が進まない
- 作業ミス
- 他部署との連携不足
- 在庫管理に問題がある
それぞれの点について詳しく確認していきましょう。
人材不足
労働力人口の減少や若者の製造業離れなど、人手不足が常態化している製造現場は数多くあります。現場での人手が足りなくなると、従業員一人当たりの業務量が増え、効率は低下しやすくなります。
また、効率化を推進するための専門知識やスキルを持つ人材の不足が、新しい技術やシステムの導入を滞らせる要因となっているケースも少なくありません。
標準化が進まない
作業の標準化が進まないことも、製造業の効率化を妨げる要因の一つに挙げられます。標準化は、作業手順や品質基準を明確にし、すべての作業者が一定の品質で業務を行えるようにすることを指し、効率化を進める上で重要な手段と考えられています。
しかし、製造業では、担当者ごとに作業方法が異なる、「見て覚える」文化が根強いなど、標準化が浸透していない現場もまだまだ数多く存在します。標準化が不十分であると、経験や能力の差によって作業の速度や精度にばらつきが生じる、無駄な時間や作業が発生するなど、生産性低下につながる可能性が高くなります。
また、作業の属人化が進み、特定の従業員に過度の業務負担がかかる、ノウハウやスキルの蓄積・共有がされないなどのリスクも高くなります。
作業ミス
作業ミスが発生すると、再作業や修正が必要になり、時間やコストの大幅な増加につながります。作業ミスが発生する要因には、従業員の経験や業務量、集中力、体調、作業環境や業務の難易度など、さまざまなものが挙げられます。とくに業務標準化が進んでいない現場や、人手不足が深刻な現場では作業ミスが発生しやすく、業務効率化が進まないことが多くあります。
作業ミスは、品質低下やコスト増加、納期遅延などさまざまなリスクにつながります。企業の信頼低下や競争力低下を招く可能性もあるため、作業ミスが頻発している場合は、早急に対策に取り掛かる必要があります。
他部署との連携不足
製品の製造には生産部門、物流部門、品質管理部門、開発部門など、複数の部門が関わっています。そのため、部署間連携が不十分であると、生産性の低下を招くリスクが高くなります。とくにデータや情報の受け渡しミスや連絡不足が発生すると、生産に大きなロスが生じることがあるため、注意が必要です。
実際の現場では、部門ごとに目標が異なっていたり、コミュニケーション不足があったりすることで、連携がうまく取れていないケースが数多くみられます。このような状況では、生産工程の最適化が難しく、効率化を進めるのが難しくなります。
在庫管理に問題がある
在庫管理が抱える問題により、製造業の効率化がスムーズに進まないケースも多くあります。
適正在庫が維持できず、在庫を過剰に抱えてしまうと、保管コストや処分コストの増大により、資金繰りに悪影響を及ぼします。反対に、在庫が十分に確保できていないと、生産計画に支障をきたし、納期遅延や顧客満足度の低下、販売機会損失などにつながります。
また、生産活動に必要な部品調達に問題が生じると、各工程が滞り、業務全体の効率が低下する恐れもあります。
関連記事:在庫管理とは?基本から効率化するツールまで徹底解説
製造業で効率化を実現するためのポイント
製造業で効率化を実現するために重要なポイントは以下の通りです。
- 業務プロセスの見直し
- 業務・データの可視化
- DX化の推進
- 設備レイアウトの最適化
それぞれについて詳しく解説します。
業務プロセスの見直し
製造業の効率化を実現するためには、まずは業務プロセスの見直しを行うことが重要です。業務プロセスを見直す際には、「3Mの削除」と「5Sの徹底」を意識すると、非効率な作業や不要な手順が見つけやすくなります。
3Mの削除
3Mとは、業務の非効率を生む代表的な要素である「ムリ」「ムダ」「ムラ」を指します。業務における3Mを排除することで、安定した生産体制を確立し、作業の効率化と品質の向上が可能になります。
- ムリ:無理な作業や過剰な負担が発生している状態。従業員の疲労やミスの増加、機械の故障などが発生しやすくなります。
- ムダ:本来必要のない動作や工程が含まれている状態。時間や資源の浪費につながり、生産性を低下させます。
- ムラ:作業の負荷や生産量が一定でなく、波がある状態。品質のばらつきや生産効率の低下を招きます。
5Sの徹底
5Sは、日本の製造業から生まれた概念で、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の5つの頭文字をとった言葉です。製造業の職場環境を整える基本的な考え方であり、生産性向上や安全確保に直結する概念として重要視されています。
- 整理:必要なものと不要なものを分類し、不要なものを処分すること
- 整頓:必要なものをすぐに取り出せるように、定位置を決めて配置すること
- 清掃:作業場を常に清潔に保ち、機械のメンテナンスを行うこと
- 清潔:整理・整頓・清掃の状態を維持し、標準化すること
- 躾:5Sを習慣化し、従業員全員が自主的に取り組む文化をつくること
業務・データの可視化
業務・データの可視化とは、IoTやBIツールを活用して、これまで把握しづらかった作業工程や生産データを数値化・視覚化することを指します。業務やデータが可視化できれば、作業のムダやボトルネックを特定し、業務改善の具体的な施策を打ち出すことが可能になります。
たとえば、機械や設備の稼働状況のモニタリングにより、生産ラインの異常や設備の故障が早期に発見でき、ダウンタイムを最小限に抑えられます。また、作業員の動線分析を行えば、作業のムダを削減し、労働生産性向上にもつながります。さらに、可視化されたデータの蓄積・分析を行うことで、需要予測や生産計画の精度向上にも役立ちます。
DX化の推進
DXは、デジタルトランスフォーメーションの略称で、AI、IoT、クラウド、ロボットなどのデジタル技術を活用し、業務プロセスを根本から変革することを指します。
たとえば、生産ラインの自動化・無人化により、作業の標準化と省人化が実現できれば、人手不足の解消につながります。また、生産管理システムを導入すれば、在庫や生産状況をリアルタイムで把握し、需要変動に柔軟に対応できるようになります。近年では、AIを活用した予測分析を導入し、設備の故障予知や品質管理の精度向上に役立てている企業も増えています。
DXの推進には、初期コストや従業員のデジタルリテラシー向上など、多くの課題が存在するのも事実です。しかし、効率化を実現し、企業の競争力を強化するためにも、自社の課題に適したDX戦略を策定し、段階的に実施していくことが求められています。
関連記事:デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?3つの成功事例から学ぶ技術戦略
設備レイアウトの最適化
設備レイアウトとは、工場や生産現場において、機械・設備・作業スペース・材料・人員の配置することを指します。設備レイアウトの方法は主に以下の4種類で、自社で扱う製品の種類や特徴、生産規模によって最適な方法が異なります。
|
特徴 |
メリット |
適用例 |
|
|
ジョブ ショップ型 |
同じ機能の機械や設備をまとめて配置する方法 |
|
金属加工 試作工場 部品製造 |
|
ライン型 |
製造工程に沿って設備を直線的に配置する方法 |
|
自動車組立 家電製造 食品加工 |
|
セル型 |
作業者を中心として道具や設備を配置する方法 |
|
電子機器 医療機器 精密部品製造 |
|
据え置き型 |
固定された製品の周りを作業者や設備が移動する方法 |
|
船舶・航空機 建設機械 発電設備 |
製造業における効率化を実現するためには、現状のレイアウトが自社の扱う製品や事業規模に適しているか、設備レイアウトの見直しを行うことが重要です。無駄な移動や重複する作業を削減し、最適なレイアウトが実現できれば、作業時間の短縮やコスト削減が可能になります。
まとめ
製造業における効率化は、市場競争の激化や人手不足といった課題を克服し、持続的な成長を実現するために欠かせない要素です。
効率化を成功させる方法には、業務プロセスの見直しやDXの推進、データの可視化、設備レイアウトの最適化など、さまざまなものがあります。そのため、自社の現状や課題を正しく把握し、最適な方法を選択することが重要です。
また、効率化は一朝一夕で達成できるものではないため、現場の意見を柔軟に取り入れながら、段階的に取り組みを進めていくことも成功のポイントといえます。